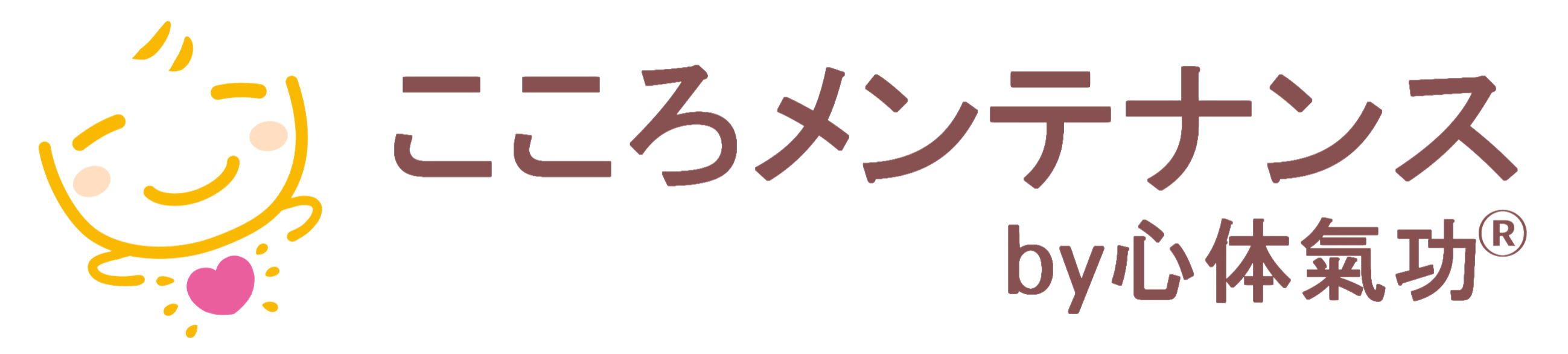吉村竜児が出来るまで その1 〜幼少期
みなさん、こんにちは^^
こころメンテナンス・インストラクターの吉村竜児です。
「こころメンテナンス」という手法は、ぼくが開発した オリジナルの手法です。
とはいえ、ぼくが一人で全部考えたわけではありません。
いろんなところで、多くの方たちとの出会いの中で 学んできたものが
組み合わさって出来てきたものです。
以前から、どのような想いで出来てきたのかを、 みなさんにお伝えしていきたいと思っていました。
しかし、それをお伝えするには、今までの経緯もいろいろお伝えしていかないと よくわからないところも出てくるわけです。
どこからどこまで話したら良いんだろう と考えると、いろんな事がありすぎてよくわからなくなってしまい、 なかなか書き始められませんでした^^;
そんなわけでとりあえず、ぼくの人生を幼少期から順に 書き出していこうと思った次第です。
かなり長くなって、所々重い話も出てくるかもしれないので、 まぁ、気が向いた方が気が向いた時に読んで頂けたら良いかなと 思います^^
というわけで、ゆるっと始めていこうと思います。

ぼくは1969年の8月6日に川崎市の幸区で生まれました。
母方の祖父母が所有していたアパートの一室に 両親と3人で暮らしていました。
隣の部屋には母の兄夫婦と3人の息子たちが住んでいて、 一番下の従兄弟はぼくと年が近かったので、よく遊んでいました。
また、2階の部屋には母の姉夫婦が2人で暮らしていました。
その頃の事でぼくがよくおぼえているのは、 両親がケンカをしていて、母が泣いている場面です。
ぼくの母は、ぼくを産んだ時はまだ大学生だったようです。
父は母より6才年上でしたが、共産党の活動をしながら 職を転々として、あまりちゃんと働いてはいなかったみたいです^^;
ぼくの母方の祖母は、祖父にとっては後妻でした。
母は10人兄弟の末っ子でしたが、祖母と直接血がつながっていたのは、ぼくの母一人でした。
祖父は、若い頃に中国から日本に渡ってきた料理人で、 同じく中国人の奥さんと川崎で中華料理屋を営んでいました。
2人の間に生まれた9人の子供たちは、日本生まれですが 家では広東語を話して生活していました。
ぼくの祖母は、元はその店の従業員だったそうです。
詳しい経緯は知りませんが、前のおばあさんが 病気で亡くなった時に、ぼくの祖母が勝手に婚姻届を出して ぼくの祖父と夫婦になることで店の乗っ取りを謀ったようです^^;
祖父の料理の腕は確かだったので、コミュニケーション手段が 今ほど発達していなかった当時でも県外からお客さんが来るような 繁盛店だったのでした。
しかし、祖母は、ぼくの伯父さん伯母さんたちに 店でただ働きをさせて、
稼いだお金を自分の親兄弟にせっせと 貢いでいたようです。
また、祖母は日本人で広東語がわからないので、 家の中では広東語の使用を禁止したため、
子供たちは広東語を 忘れてしまい、祖父は家の中でも孤立するようになっていました。
そんな中、ぼくの伯父さん伯母さんたちは 高校にも行かせてもらえないのに、
母は中学から青山学院の中等部に入るなど、 同じ家の中で兄姉たちと
明らかに違う待遇を受けていました。
もちろん他にもいろいろ理由はあったと思いますが、 ぼくの母はそういった環境で育っていく中で、
実の母親に対して不信感を募らせていったようです。
そんなこんなで、大学生の頃に父と知り合ってすぐに結婚したのも、
「自分の母親から早く離れたい」という思いからでした。
ところが、ちゃんとした定職に就いていなかった父にとっては、
ちょっと金持ちの家の娘と結婚すれば生活が安泰だという 思惑があったようです。
なので、祖母の反対を押し切って結婚はしてみたけれど、
結局は自分の両親が所有するアパートに家賃タダで住み続ける という状態が続いていました。
ぼくの祖母はそうとう支配的で、思い通りにならない相手には かなり激しく、
しかもしつこく攻撃をする人でした。
当時の母が抱えていたストレスもそうとうだったんだろうなと思います。
ぼくを妊娠した時も、何度も堕ろせと言われたそうです^^;
そこは堕ろさない選択をしてくれて、ぼくからは「ありがとう」としか言えません。
そんなだったから、ぼくが生まれた時には、母は精神的に かなり参っていて、
たまたま父が持っていた食べ物公害に関する 本を読んだことがきっかけでノイローゼになってしまいました。
母はありとあらゆる食品が有害だと思い込んでしまい、 離乳期のぼくに何を食べさせたら安全なのかわからなくなっていったのです。
丸一週間ハチミツを水で薄めたものだけを与えて、 危うくぼくを死なせかけました。
ぼくがみるみるやせ細っていくのを、父や伯母たちが気づき、
問いただしたことで、ぼくは一命を取り留めました。
とはいえ、当時のぼくはそんな事情はつゆ知らず、
どこの子たちとも同じように両親のことが大好きでした。
ただ、両親が良く言い争いをしていて、母が泣かされているところを見ていたので、
「ぼくがお母さんを守らなきゃいけないんだ」と思っていました。
また、ぼくががんばることで、「両親が仲良くなってくれるんじゃないか」みたいなことも思っていた気がします。
しかし、物心ついてちょっと知恵が付いてくると、今度は違う考えが出てきました。
母親が泣かされているのにもかかわらず、父から離れられないでいるのは
「自分がいるからなんじゃないか」みたいなことも考えるようになって、
子供心ながらにかなり悩んでいた気がします。
その頃、母に「お母さん大好き。ぼくお父さんがいなくても大丈夫だからね」 と
言ったのをなんとなくおぼえていて、後に母からもそのことを聞きました。
話の前後関係はよくおぼえていないのですが、 当時母は父との言い争いがきっかけで、
幼いぼくと父をおいて 二週間ほど家出をしたことがあるそうです。
たぶん、そのことで、両親が別れるならぼくは母親の方を選択するから
「一緒に連れて行って欲しい」という意思表示を母にしようとしていたんだと思います。
ただ実際には、ぼくが5才の時に両親が離婚した際、 子どもをおいて家出をしたことが
不利に働いて、母は離婚調停でも 誰からも味方してもらえず、
ぼくの親権を手放すことになりました。
しかし、離婚当時、父は定職についておらず、ぼくを引き取って住む場所もなかったため、
生活の基盤が出来てからぼくのことを迎えに来るという条件で、
それまで母と二人暮らしをすることになりました。
当時、幼かったぼくは離婚の意味がよくわかっていなかったため、
実際には父は一緒には暮らしていなくて、たまに顔を出していたのですが、
ぼくは「父は一緒に暮らしているけど外出がちになっていた」と思っていました^^;
そんなこんなで、小学校に入るちょっと前ぐらいから、 母との二人暮らしが始まりました。
===================
しんどい話を長々と書いてしましたが、大丈夫でしたか?^^;
最後までお読み頂いてありがとうございました♪
そして、おつかれさまです^^
次回は、母との二人暮らしの頃の話を書きたいと思いますので、 よろしくお願いします☆^^