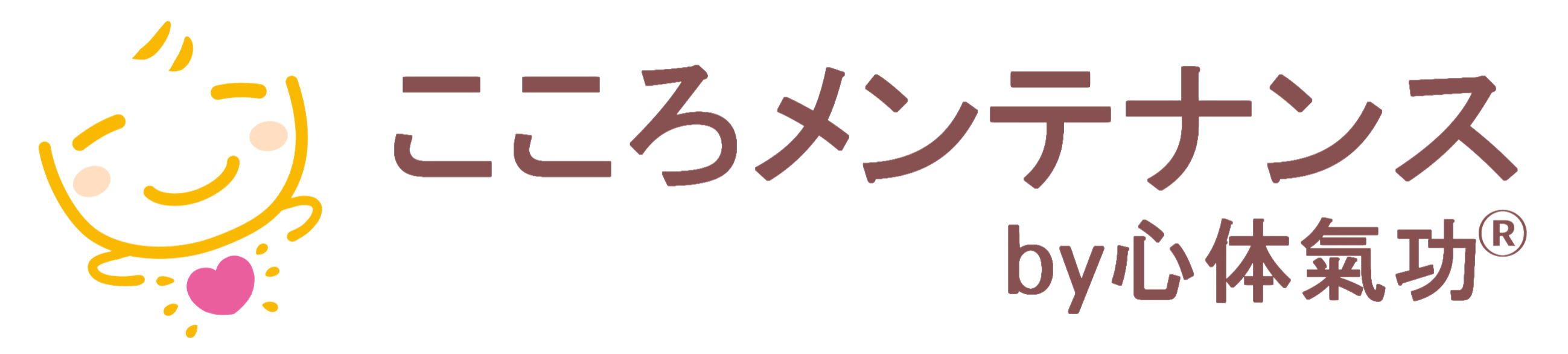吉村竜児が出来るまで その2 ~母との二人暮らし
みなさんこんにちは^^
こころメンテナンス・インストラクターの吉村竜児です。
前回から引き続きお読みいただいている皆さま、ありがとうございます♪
しんどい話を長々と書いてしまいましたが、具合悪くなったりしませんでしたか?
ぼくの方は何とかあまり間を空けずに続きを書き始めることが出来ました^^
今回もけっこうしんどい話になりそうな気がしますが、
しばしお付き合いください^^;
あ、そもそも興味ない人や、ぼくみたいに長文を読むのが苦手な人は
スルーしてくださいね^^

ぼくの両親はぼくが小学校に上がるちょっと前に離婚していたのですが、
ぼくにはその辺の生活の変化がよくわかっていませんでした。
ちょうど同じ頃に隣町の一軒家に引っ越しをしたのですが、
これはもともと祖母が持っていた別の物件に空きが出たので、
両親とぼくが3人で暮らすために改修工事を行った物でした。
つまり、家の改修が始まった時には両親はまだ別れていなかったのですが、
新しい家に引っ越してから父親を家であまり見かけなくなったので、
引っ越しのどさくさの間に離婚も行われていたようです^^;
父はたまに会いに来て、ぼくに自転車の乗り方を教えてくれたりしていました。
よくよく考えてみると、それもあまり頻繁ではなかったので、
当時のぼくが両親の関係性についてどう捉えていたのかが、
はっきりしなくて不思議な感じです^^;
父とは近くの公園で、二回ほど自転車の練習をしたことをおぼえています。
一回目は、後ろで自転車を支えてくれていると思っていた父が実は手を離していたことに気づき、
後ろを振り返ったとたんに転んで、膝をひどくすりむきました。
ぼくが膝から血を流しながら家に帰ったことで、母がものすごい剣幕で
父にわめき散らしているのを見て
「ぼくは大丈夫だから、お父さんを責めないで。
転んでもいいから、自転車に乗れるようになりたいんだ」
というようなことを一生懸命言っていたのをおぼえています。
二回目はその日のうちか、別の日だったかはよくおぼえていません。
ただ、転んだのは初回の一回だけで、その後はすぐに乗れるようになりました。
有頂天になって公園の中を何周もしながら、こんな経験をさせてくれた
父をすごく頼もしく思って、父のことがますます好きになっていました。
一方、ぼくの母は小さい頃から外では遊ばせてもらえず、
家の柱に縛り付けられて勉強ばかりさせられていたので、
自転車にも乗れず、かなりひ弱な印象の人でした。
父は別れ際に、
「まだ道路を走るのは危ないから、お父さんが良いって言うまでは
自転車は公園の中だけで練習するんだぞ」
と言って去って行ったのですが、
その後はかなり長い間現れませんでした^^;
そのため、ぼくは自転車に乗れるようになった後もけっこう長い間、
公園まで自転車を押していって、公園の中をしばらくぐるぐる回ってから、
また自転車を押して家に帰るという不思議な遊びをしていました。
ただ、近所に友達が出来ると、
「あっちにも面白い公園があるから自転車で行こうよ」
とか
「自転車で駄菓子屋に行こう」
といった、誘いを受けるようになりました。
初めのうちは
「お父さんがダメって言うから」
と言って断っていたのですが、
そのうちに誘惑に負けて、自転車で隣町ぐらいまでは
遊びに行くようになっていました。
ただ、父の言いつけを守れなかったことにはものすごく罪悪感を感じていて、
父がなかなか会いに来てくれないのは、
「ぼくが父の言いつけを守らなかったからなんじゃないか」
みたいなことも考えるようになっていました。
引っ越してから程なくして、入学準備の説明会やら
知能検査などで近くの小学校に行きました。
近所で友達になった子たちも来ていたので、
そこの小学校に通うのを楽しみにしていたのですが、
実際に通い始めたのは家から2キロぐらいのところにある川崎区の小学校でした。
当時市役所で働いていた母は残業などで帰りが遅かったため、
母の実家の近くの小学校に通わせるようにと、祖母からの提案があったからです。
とは言っても、祖父母の家はいつも忙しい中華料理屋だったため、
学校から帰ってもたいがいは「外で遊んでなさい」と言われて落ち着かないので、
なんだかんだで家に帰って鍵っ子生活をするようになっていました。
実際、母と二人で暮らしていた家の隣では、伯父さん夫婦が中華料理屋を営んでいたので、
食べるものにも困らず、至って快適でした。
小学校では男の子たちの戦いごっこみたいな荒い遊びにはあまりついて行けませんでした。
ですが、乱暴な子にいじめられそうになったら守ってくれる子もいて、
クラスの雰囲気は悪くはありませんでした。
担任は初老の男性の先生でしたが、明るく活発な雰囲気で、
クラスの子供たちからもかなり慕われていたと思います。
ただ、ぼくは学区外から通っていたため、放課後に学校の友達と遊ぶことが出来ず、
近所の友達とも学校の話題で話すことが出来ないため、
ぼくにとっての子供同士の人間関係はどんどん希薄になっていきました。
その辺のストレスも関係してか、小学校に上がってから
ぼくは頻繁におねしょをするようになっていました。
毎晩、母はぼくを寝かしつけるために本の読み聞かせをしてくれていました。
その時は優しくて面白くて大好きな母が、朝になると鬼のような形相でわめき散らしながら、
おねしょで濡れた布団をぼくの顔にぐいぐい押しつけてくる。
というのが、朝の日常の風景になっていました。
その頃は、お母さんがこんなに苦しんでいるのはぼくがいるからで、
ぼくがこのままいなくなればお母さんは自由になれるだろう、
今日こそここでぼくは消えてなくなって、ぼくもお母さんも自由になれるはずだ。
みたいなことを思いながら、意識が遠のいていくのを感じていました。
しかし、いつもふと気がつくと小学校までの通学路にあった
大きな製菓工場から漂ってくるチョコレートのむっとする臭いで
意識を取り戻し、何が何だかよくわからないままに、
小学校に向かって歩き出していました。
朝ご飯に何を食べたのかもわからないし、どうやってそこまで
たどり着いたのかもよくわからないという感じで、
今思うと、状況がよくわからないままでもとりあえず流れに乗って
その場を切り抜けるという習慣が身についたのもこの辺からかもしれません。
その頃は登校途中によく仲の良かった野良犬が出迎えてくれて、
しばらく一緒に歩いてくれたので、そのうちに気分が晴れてきました。
その犬は近所のボス的な犬で、かなり広い範囲を縄張りにしていたようです。
祖父母の家で飼われていた犬たちも、新しい首輪を付けてもらうと必ず
この犬に見せに行っていました。
けっこう大きな犬でしたが、とても警戒心が強くて利口だったため
保健所の野犬狩りにつかまることもなく、大人たちは触ることも出来ませんでした。
唯一ぼくには良くなついていて、なでることも出来ましたが、
祖母に言われて首輪を付けようとしたら逃げられてしまいました。
祖母の家の近くの人たちはこの犬を“とうきちろう”と呼んでいたのですが、
ぼくは、とうきちろう にはずいぶん助けられていたと思います。
当時の川崎区は、ホームレスと野良犬が至る所にいる、かなり物騒な地域でしたが、
ぼくが野良犬から吠えられたり追いかけられたりすることが全くなかったのは、
今思えばとうきちろうと仲が良かったからだと思います。
このような朝の光景は、ぼくのおねしょが終わるまで続きました。
ぼくがおねしょをしなくなったきっかけは、非常に単純なものでした。
ぼくがおねしょをしていた時は決まって前の晩に母がぼくを寝かせ付ける時に
「ねしょうべん物語」という本の読み聞かせをしている時だということに
母が気づいて、その本の読み聞かせをやめたことで、
ぼくもおねしょをしなくなりました。
この「ねしょうべん物語」という本は子供向けの短編集で、
すべてのエピソードはおねしょをしてしまう子供が、何かのきっかけで
おねしょをしなくなるという話でした。
この主人公たちの周りの大人たちはみなやさしくて、
主人公がおねしょをしても怒ったり責めたりはせずに、
主人公と寄り添って、一緒におねしょを克服するためのアイディアを
考えたり実行したりしてくれる人たちでした。
ぼくは心のどこかで、自分の母がこの本に出てくる大人たちのように
ぼくを許して受け入れてくれることを期待していたのですが、
結局それは実現せずに、「ねしょうべん物語」の読み聞かせがなるなると同時に、
ぼくの“おねしょの物語”も終わりました。
そうこうしているうちに小学校2年生の三学期も終わり、
春休みが明けたら3年生という時に父がぼくのことを迎えに来ました。
ぼくは、母と離婚して親権を持った父がぼくを迎えに来るというのが
いったいどういうことなのかはまったくわかっていなかったため、
母に元気に「いってきます!」と言って、父の車に乗り込みました。
こうしてぼくにとっての一回目の母との二人暮らしも終わりを告げました。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました^^
前回に引き続き、今回もまた輪をかけてしんどい話になってしまいましたね^^;
次は父との二人暮らしの話ですが、この頃はぼくの人生の中でも
最もしんどかった時代なので、あまり暖めすぎてまたモヤモヤしてこないように、
なるべく早くサラッと書くようにしたいと思います^^
それでは、次回もよろしくお願いします☆