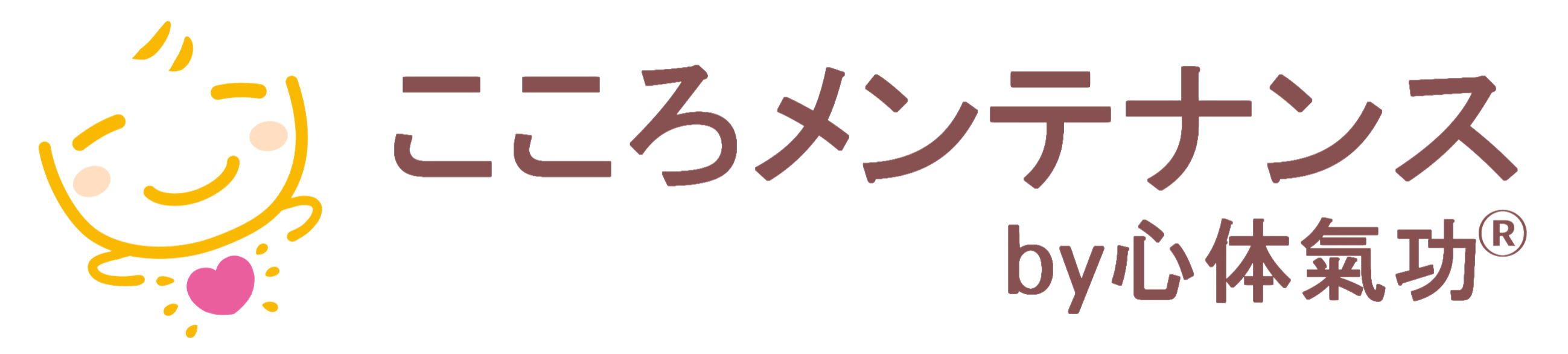生まれて初めて感動で涙を流した記憶
確か小学校に上がる前の、保育園の年長さんか年中さんの頃だったと思います。
当時ぼくは食べることがあまり好きではなくて、周りの人たちが心配するぐらいにやせ細った子供でした。
ぼくが生まれてすぐぐらいの頃に、ぼくの母が父からすすめられて「食べ物公害」に関する本を読んだことがきっかけでノイローゼになり、食品添加物や調味料を極端に恐れるようになってしまいました。
そのため、離乳期のぼくに離乳食を食べさせることが出来なくなり、0歳児だったぼくにハチミツを白湯で薄めたものだけを与えていたらみるみるやせ細っていきました。
1週間ぐらい経ったときにようやく父や周りの人たちが異常に気づいて、ぼくは一命を取り留めたそうです。
その後も、母は味がないものばかり作るようになり、物心ついた頃には、ぼくにとっての食事の時間は、親から「食べなさい」と言われるからしかたなく目の前の物を我慢して片付けていくだけの苦痛に満ちた時間になっていました。
その間にも両親からは、「世の中の食べ物がどれだけ毒にまみれているか」、「安全なのはうちの食べ物だけだ」みたいな話を延々とすり込まれていました。
なので、よその人から食べ物をもらって食べるということもまずありませんでした。
そんなある日、どういったいきさつだったかは忘れてしまいましたが、当時住んでいたアパートの隣の部屋に住んでいた従兄弟たちと遊んでいたら、伯母さんが「もうお昼だから竜ちゃんもうちで食べていきなさい」と言いました。
ぼくは毒が怖くて「いらない」と言ったのですが、伯母さんは「今日はカレーだよ。子供はみんなカレーが大好きなんだから、ひとくちだけでいいから食べていきなさい」と言って引き下がってはくれません。
ぼくは渋々「じゃあ、ひとくちだけでいいんだね?」と言ってカレーをひとくち、口の中に入れました。
すると、今まで感じたことのない衝撃が全身を貫いて、目から涙がボロボロとこぼれ出しました。
「美味しい」という感覚をぼくが初めて知った瞬間でした。
その後は、ひたすら涙を流しながらカレーを一皿完食しました。
その後のことはあまりよくおぼえていません。
もしかしたら、よその家で食事をしたことで両親から怒られたかもしれません。
ぼく自身が日常的に食事を楽しむことが出来るようになったのは、もっとずっと後だったので。
ただ、この時の全身が打ち震えるような感覚は今でもよくおぼえています。
幸せや感動って、すぐ近くにあっても何かの思い込みや恐れにとらわれて、自分から遠ざけているものもたくさんあるかもですよね。
ぼくは、みんなが自分の近くにある幸せを感謝して受け取れるようになっていったら、世界中がちょっとずつだんだんと幸せになっていくんじゃないかなと思って、地上楽園化計画を進めています。